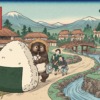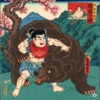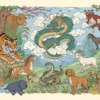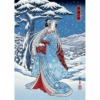わらしべ長者:秒速で億万長者になる方法(ただし運ゲー)
わらしべ長者
むかしむかし、あるところに、とても貧乏な男がいました。あまりにも貧乏なので、男は「このままではいけない。なんとかして貧乏から抜け出したい」と神様にお願いしました。
すると、夢の中に神様が現れて、こうお告げになりました。「朝起きて、最初に手にしたものを大切にしなさい。それがお前の運を開くきっかけとなるだろう」
翌朝、男が目を覚ますと、すぐそばに一匹のアブが飛んでいました。男はそれを手で払いのけようとしましたが、アブはしつこくまとわりつきます。男はイライラしながらも、そのアブを捕まえ、道端に落ちていた藁でアブを結びつけました。
「これが神様のお告げの品か」と男は思いながら、その藁の先にアブを結びつけたまま歩き始めました。
しばらく歩いていると、男は道端で泣いている子供に出会いました。子供は喉が渇いているようで、泣き止みません。それを見た男は、「かわいそうに」と思い、藁に結んでいたアブを子供に差し出しました。子供はアブを見ると喜んで、泣き止みました。
それを見ていた子供の母親が、「お礼といっては何ですが、これを差し上げましょう」と言って、蜜柑三つを男にくれました。男は蜜柑をもらい、また歩き始めました。
さらに歩いていると、男は喉が渇いて苦しんでいる旅人に出会いました。旅人は今にも倒れそうです。男はかわいそうに思い、先ほどもらった蜜柑を一つ、旅人に差し出しました。旅人は大変喜び、「おかげで命が助かりました。これは私のお礼です」と言って、上等な布三反を男にくれました。
男は上等な布をもらい、さらに歩き続けました。今度は、目の不自由なお侍さんが、馬から落ちて困っているところに遭遇しました。お侍さんは、目が見えないため馬に乗ることができません。男は上等な布を使ってお侍さんの馬を丁寧に引き起こし、またお侍さんが馬に乗るのを手伝いました。
お侍さんは大変感謝し、「あなたは親切な方だ。これは私のお礼です」と言って、自分の立派な馬を男にくれました。男はまさか馬が手に入るとは思わず、驚きながらも馬を連れて歩き続けました。
日が暮れてきた頃、男は大きな屋敷の前を通りかかりました。すると、屋敷の主人が困った様子で出てきました。「実は、私の馬が病気で動けなくなり、今すぐ遠くまで行かなくてはならないのに困っているのだ」と屋敷の主人は言いました。
男は、「もしよろしければ、この馬をお使いになりませんか?」と、自分がもらった立派な馬を差し出しました。屋敷の主人は大変喜び、「これは助かった!お礼に、この屋敷と田畑、そして娘を差し上げましょう」と言いました。
こうして、貧乏だった男は、一本の藁から始まり、物々交換を繰り返すうちに、立派な屋敷と広大な田畑を手に入れ、美しい娘を妻に迎え、大金持ちになりました
わらしべ長者の物語は、日本の昔話として広く知られ、親切心や知恵の大切さを教えてくれる良い話とされています。しかし、現代の視点から見ると、いくつか「突っ込みどころ」があるのも事実です。
わらしべ長者への突っ込みどころ
この物語をよく読んでみると、以下のような疑問が湧いてくるかもしれません。
1. 「最初に手にしたもの」がアブと藁って、幸運すぎるのでは?
神様のお告げで「最初に手にしたもの」がアブと、そのアブを結びつけるための藁だったというのは、いかにも出来すぎた展開です。もし最初に手にしたものが、例えば道に落ちていた石ころだったらどうなっていたのでしょう? それが幸運のきっかけになるかというと、ちょっと想像しにくいですよね。これは物語を成立させるための、ご都合主義的な設定と言えるかもしれません。
2. 物々交換の効率性が良すぎる!
子供が泣き止んだだけで、母親が価値のある蜜柑をポンと渡す。喉が渇いた旅人に蜜柑を一つあげただけで、上等な布三反が手に入る。そして、馬から落ちたお侍さんを助けただけで、自分の立派な馬をくれる。最後の屋敷の主人が、馬を貸しただけで屋敷と田畑、さらに娘までくれるという破格の交換。
現代の市場経済で考えれば、これほどスムーズで、しかも交換するたびに価値が飛躍的に上がる物々交換はありえません。まさに「棚からぼたもち」の連続であり、現実離れしています。
3. 他人のものを躊躇なく受け取りすぎでは?
旅人やお侍さん、屋敷の主人など、皆が「お礼です」と言って、相当な価値のあるものを躊躇なく差し出しています。現代なら、「何か裏があるのでは?」とか「そんなに高いものをもらっていいのか?」と考えるのが普通でしょう。もちろん、当時の価値観や人々の親切心を表しているのかもしれませんが、あまりにもあっさり受け取る主人公にも、ちょっとした図々しさを感じてしまうかもしれません。
4. 娘がおまけ?
最後の交換で、屋敷と田畑だけでなく「娘」までお礼として差し出されるのは、現代の感覚からすると非常に問題のある部分です。娘がまるで物のように扱われ、交換の対象となっている点は、女性の権利や人権といった観点から見ると、とても受け入れられるものではありません。これは昔話ならではの価値観として理解するしかない部分です。
もちろん、これらは昔話を現代の視点で深読みしすぎた「突っ込み」であり、物語本来の意図は「小さな親切が巡り巡って大きな幸運を呼ぶ」という教訓にあることは間違いありません。しかし、こういった視点で物語を改めて読み解いてみるのも面白いかもしれませんね。 「わらしべ長者」、あらためてこうやって全文読むと、ツッコミどころ満載ですよね!昔話ならではの、おおらかで都合の良い展開が魅力ですが、現代の視点から見ると色々考えてしまいます。